テキスト > 松下学
2012年1月26日から2月19日の東京都千代田区外神田6-11-14の205号室
執筆 : 松下学(Rad.Commons)
*2012年1月の齋藤祐平個展「脈絡」に寄せた文章を一部加筆修正。
齋藤祐平は画家である。1982年に日本の新潟に生まれ、幼少の頃から絵に親しみ、今は東京に拠点を移して変わらぬ情熱で絵を描き続けている。 2002年に東京工芸大学厚木校舎の空きロッカーで自ら開催した初めての個展『Counting Breeding』以来、電話ボックスや空き店舗のような都市の様々な環境を活かして作品を発表し、ギャラリーでの展示も行いつつ、さらには自作本を媒体とした様々な実験、OPAOPA・Night TV・聞き耳といったグループでの制作、画家の仲間たちを集めてのグループ展やライブペインティングの開催など、積極的に活動の幅を広げながらあちらこちらへとその足跡を残してきた。
作家としての出発からおよそ10年となる2012年1月26日より行われるIsland Mediumでの個展『脈絡』は、こうした齋藤の充実した活動からは意外に思えるが、齋藤自身がそう語るように「初めてのホワイトキューブでの個展」となるものだ。たしかにこれまでの齋藤の活動は、ギャラリーで絵をただ静かに展示するといったいわゆる正統派の画家活動からはほど遠い印象を与える。即興性や集団性を活かしたライブペインティングの一日展シリーズ「間欠泉」は、古式ゆかしい画家の厳かめしさよりはセッションに興じる音楽家のような軽やかさを感じさせる。また、古書店やゴミ収集所といった都市ネットワークの特異点への作品投下には、空間を巡る政治へと機動的に介入するグラフィティのような機敏ささえ見出すことができる。とりたててギャラリーや美術の制度に反抗しているというわけではないものの、目に映るすべてのものに絵画の可能性を見出してしまう齋藤は、その先に広がっているかもしれないまだ見ぬ光景を求めて、内よりも外へ、ふらりと旅に出るように次の一歩を踏み出すのである。そのようにして自然に身の周りに広がる世界に飛び込み、他者や空間といった環境と繋がり、そこに刻まれた記憶や歴史との対話を介して、齋藤は自分ひとりの世界に留まらない表現を育んできたといえる。
そんな齋藤にとって、ホワイトキューブという隔たれた何もない部屋は、その漠然とした空虚さゆえにむしろ困難な挑戦として現れただろう。そこで齋藤が出した答えは、その白い部屋をどこまでも自由なニュートラルな空間として無批判に受け入れることでも、あるいはそのわざとらしい無菌状態に批判的に介入することでもなかった。むしろ齋藤は、まるで知らない街でふと迷い込んだ風変わりな場所を堪能するかのように、アートのためだけに作られたこの不自然な環境に入り込み、その不自由さを積極的に活かすために、徹底して意識的に正統派の絵画展を行うことを決意したのである。おそらく当人にとっても予想外なことに、このどうしようもなくアートに特化したホワイトキューブという環境を与えられたことで、齋藤は改めて画家としての自分に正面から向き合うことになったのである。こうして、当初『木馬Xと石牛Y』と題されていた展示は、ここに至るまでの齋藤のルーツを表すべく『脈絡』という大胆不敵な名前を新たに得ることになり、齋藤がこれまでの活動で身に付けたすべての技法と着想を駆使した作品がこの展示のために新たに制作された。自らを画家として認識するうえで、そしてそのことを公に表明するうえで、齋藤はホワイトキューブという環境を発見し、まさにそのように活用したのである。その意味でこの『脈絡』は、これまでの多様な活動にひとりの作家の足跡として一本の筋を通す、10年の準備期間を経て開かれることとなった画家・齋藤祐平の初めての個展として見ることも、あながち見当違いではないだろう。
そうして真っ向から作品のみを突きつけられてみると、齋藤祐平は画家であるということのほかに語りようがないことが改めてよくわかる。齋藤の活動の表立った多彩さの背後には、世界と絵画をお互いを巻き込んでいく、唸りを上げるエンジンのようなひとつの運動がある。世界の境界を媒介とみなすことで貪欲に駆動するこの絵画エンジンは、それが空きロッカーであれギャラリーであれ、身の周りの世界の様々な環境に遭遇することで、各々の生態に応じたイメージや行動を導き出していく。しかしこうして生じる多様さにもかかわらず、その根底にはあるのは、世界に触れ、何かを感じ、それを描くという、極めて単純な画家の営みである。だからこそ齋藤は、言葉や戦略を尽くして作品にそれらしい理由やわかりやすい主張を与えることもせず、世界との驚きに満ちた遭遇において感覚が捉えたイメージを形にする欲求にほとんど盲目的に没頭してきた。素材と環境との戯れから生まれてくる作品のほとんどは、これといった主義や主題もなく、日常の中の何でもないものをただ様々に描いたもので、往々にして純粋に視覚的な刺激と何かしら形象的な記号のあいだでどちらつかずに揺れている。そのスタイルは表現的でも構成的でもあり、技法は正体も目的も不明な実験と独創に溢れ、色彩と筆触は具象と抽象を曖昧にもてあそんでいる。そうして創り出されるものは、ときに先進的であったり、同時代的であったり、あるいは凡庸であったりするものの、そのすべてを平等に引き受ける齋藤の活動は、それを世代や文脈へと意味づけようとする試みをあえなく失敗させるか、せいぜい偶然の一致に留まらせる。だからこそ正確を期すほどに、語り手には「齋藤祐平は画家である」という退屈で率直な言葉だけが残される。
そんな齋藤祐平の作品にもし意味を求めたり、あるいは与えようとするならば、齋藤自身はそんなものはないと言うだろう。もし技術を問われれば、それさえないと言うかもしれない。そして情熱を求めれば、たとえあるとしても、はぐらかされるのが目に浮かぶ。しかし作品の価値を問われたとすれば、齋藤は必ず「ある」と答えるだろう。その価値を確信するからこそ、ただ描くという最も単純であるゆえに最も困難なやりかただけで齋藤は画家であることを貫いてきたのだ。しかしそのひたむきさは、作家としての純粋さをどこかの誰かに向けて訴えようとするものではなく、ただ目の前に広がる世界に次々と欲情するあけすけでわがままな画家の欲望そのものだ。偏った競争と教養のなかでせわしく意義を求めるアートワールドの言葉遊びが絵画に油断しているあいだに、齋藤は変わらぬ情熱で途絶えることのない欲求を満たし、絵画という尽くせぬ可能性を飽きることなく貪っていくだろう。『脈絡』はいわば、絵画という表現とホワイトキューブという空間のどうしようもない無意味と独善性に対して、同じだけ無意味で独善的な存在としての画家・齋藤祐平が初めて正面から向かい合う場所だ。ここから何が始まり、それがやがて何を成し遂げ、そのときこの『脈絡』という展示がどのように記憶されることになるかは、今はまだ誰も知らない。
※今回の展覧会は、今までの活動で試みる機会のなかった「ホワイトキューブでのシンプルな絵画展」をあえてやろうという意識から出発した。典型的な形式のもとに行われる展覧会につきものなのは、作家以外の人間が書いた煽り文である。よってその点も本展では踏襲し、松下に文章執筆を依頼した。齋藤からは「今回の個展とそれ以前の活動との関連性(または非関連性)がわかるような文章にしてほしい」ということのみ伝え、文章には明らかな間違い以外修正を行っていない。(齋藤)
※この文章をホームページに掲載するにあたり、松下より「内容を一部加筆修正したい」と要望があった。修正後の文章を読んだところ大意は変わっていないように感じたので、当ページではその文章を掲載している。この修正にも、齋藤は内容変更の指示などは行っていない。(齋藤、2012/11/16)
[INTERVIEW]
齋藤祐平インタビュー|KALONSNET
公開日:2010/12/24

[EXHIBITION]
個展『脈絡』
2012/01/26 - 02/19
@island MEDIUM(東京、神田)
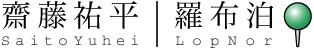

 PAGE TOP
PAGE TOP